





熊川葛と頼山陽
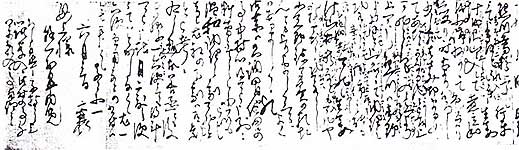
頼山陽の母への手紙 「熊川葛」のことが見える
江戸時代の有名な儒者、頼山陽が、広島にいる母が病気の時、
天保元年(一八三〇年)六月三日に京都から出した手紙の中に、
熊川産の葛粉を送ったことが詳述されている。
そこには「この度、熊川葛粉を上げ申し候。
行平(ゆきひら)にてよきほどにとき、生姜汁を沢山に入れて煮立て、
手を停めずねり候て、色スッパリ変わり侯時、火よりおろし、
少しづつはさみ切り、まるめて、
あたたかなる内に召し上がられ然るべしと存じ奉り候。
又々あとより上げ申すべく侯。熊川は吉野よりよほど上品にて、
調理の功これあり候。
潤肺の能もこれあり候間、然るべく候」とある
(儒学者、近藤啓吾先生の御教示による)。
親孝行の山陽が、母の病気に驚いて、
早速、京都で求めた熊川葛を送っているのである。
「葛」といえば吉野といわれる吉野葛よりも、
熊川葛は「よほど上品」といわれた晒葛が、
若狭の熊川で生産され、
出荷されていたことを決して忘れてはならない。
この意気込みに燃えて熊川では、
戦後低調となっていた葛粉の生産に、
有志たちが相集まって葛根の掘り起こしから晒葛の精製まで、
力を入れることとなった。
そして現在は、ただ一軒ながら伝統的な生産が、守り続けられている。
 |
 |
|---|
昔使用された熊川宿の判
熊川の郷土料理として私の第一に挙げたいものは、
やはりこの葛料理である。
くずまんじゅう、くず刺身、ごま豆腐、鱒などのあんかけ、
くずようかん、ぎんなん豆腐、などなど。
いつか、熊川で作られる葛料理がNHKテレビで全国に紹介されたこともある。
やはり、みんなに最もなじみ深く、てっとり早いものは「くずまんじゅう」であるが、
熊川のそれは昔から中に小豆の餡を入れないで、砂糖をかけて食べるのが特色であった。
京都の和菓子や精進料理の名声も、
若狭の熊川葛に負うところが大きかつた、といわれる。
郷土史家 永江秀雄
 |
 |
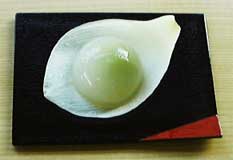 |
|---|
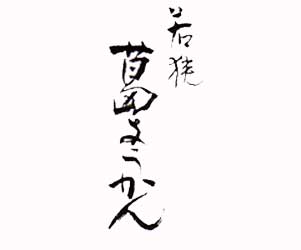
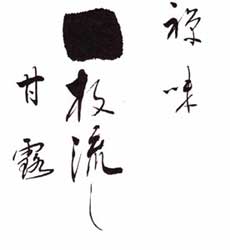 |
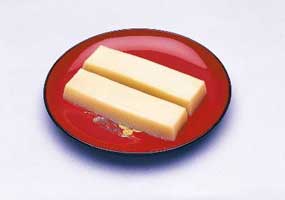 |
|---|
 |
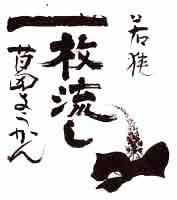 |
|---|